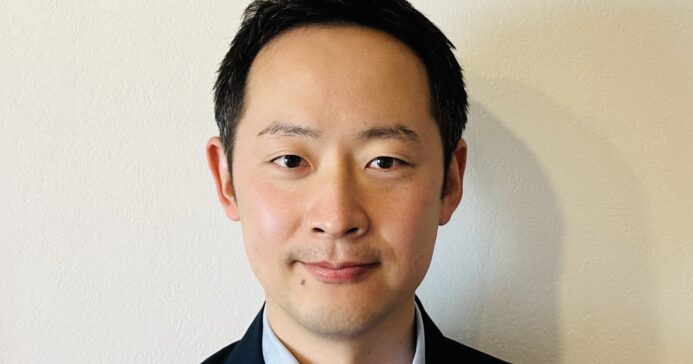淺見 知秀(株式会社みちのりホールディングス ディレクター)
略歴:
埼玉県菖蒲町(現久喜市)出身、筑波大学で都市計画、交通計画を学ぶ。
JR東日本にて、新駅建設・新幹線高速化プロジェクトなどに従事。その後、国土交通省にて、都市計画分野の政策立案、自治体支援業務に従事。小山市に出向時は、都市整備部長・技監として、都市計画、公共交通分野の指揮監督に従事する。現在、みちのりホールディングスにて、グループ各社に関わる交通計画の策定・支援、新モビリティサービスの開発・普及等に従事中。
著者:片桐暁
監修:筑波大学教授 谷口綾子
インタビュー:筑波大学修士課程(2023年度修了)溝口哲平
(2023年12月29日インタビュー実施)
文字起こし/編集:筑波大学修士課程1年 大月崇義
Introduction 「地域モビリティプロデューサー」とは
日本の地域公共交通は危機に瀕しています。鉄道や路線バスの多くは不採算路線となっており、減便か、最悪の場合には廃線や撤退を余儀なくされています。これは取りも直さず、全国で多くの交通弱者1が生まれていること、そしてこれからも生まれ続けることを意味しているでしょう。都市部のようには公共交通等の交通網が発達していない、地方住まいの人々は、クルマを運転できないというだけで、誰もが交通弱者になり得るのです。
こうした状況で重要となってくるのが、「地域モビリティプロデューサー」の存在です。この言葉は造語ですが、特定の地域においてモビリティ(公共交通を始めとした、人々の移動を可能とする力)をプロデュース(既存のシステムをうまく組み替えたり、新しい仕組みを生み出したり)していけるような、能力および権限を併せ持った人物を意味しています。この文章は、現在、地域モビリティプロデューサーの候補と目される人々に行なったシリーズインタビューを、当人の語りを中心にして構成し、日本の地域公共交通のこれからを、その“語り”から展望しようとするものです。
Part I 自分自身を語る
――淺見さんは、何を原動力として現在のような活動を始め、そして現在まで続けていらっしゃるのでしょうか。キャリアの経緯とともにお聞かせください。
学部3年の時に茨城県の土浦市で行なったマスタープラン実習が、自分にとってのターニングポイントでした。ちょうど土浦からマルイがなくなって、中心市街地がどんどん衰退していくみたいな状態を、どういうまちに変えていくかを考える実習だったんです。そこで、バスに乗る人がどんどん減って逆に渋滞は増えているという、典型的なモータリゼーションの課題に人生で初めて直面しまして、「ああ、こんな酷いことがあるんだ」と思ったんですね。若い自分にとっては、日本の街が衰退しているところを初めて見る経験だった。それがすごく強烈で、この問題を解決しなきゃいけないなと思ってずっとやっているという感じです。 筑波大学の社会工学類に進んだのは、文系でもなく理系でもなく「自分は何がやりたいんだろう」という選択肢保留の結果だったんですが、マスタープラン実習によって、「これは問題だな」という、何かこう、トラウマじゃないですけど大きなきっかけになって、その後は、その問題を解決するための選択肢をどんどん選んでいきました。
そのあとは、在籍していた筑波大学の都市交通研究室でMM(モビリティ・マネジメント)に出会って、「MⅯってすごい!」と思って、その思いで、いまでもやっています。その後にJRに就職しました。なぜかといえば当時、郵政民営化真っ只中で、「公から民へ」みたいな社会的風潮があったんですよね。それで「やっぱり民で解決するべき」と思って、交通事業者のJRで「公共交通をよくすることで世の中が良くなる」と思って入りました。けど、そこで民間企業の限界を感じたり、鉄道だけに縛られないことをもっとやりたいなと思って、国土交通省に転職しました。
それで、いまに続く原動力は、やっぱり小山市への出向ですね。小山市でようやく、土浦市のマスタープランの時の問題意識を解決できるような現場に行けたわけなんです。「いやー、やっとできるな」と思いました。
本当にラッキーだったのは、小山市は土浦市とほとんど同じ都市規模で、同様の問題を抱えていて、その中で立地適正化計画とか、総合都市交通計画とか、地域公共交通計画とか、そういったものを全部1から考えてつくる時期に、そのポジションに、偶然にも僕が置いてもらえたということですね。かつ、それを実行する機会と予算を得たので、小山市のコミュニティバスである『おーバス』の利用促進にまつわる、一連のプロジェクトを手がけることができた。それで、ここでの色々な経験がまたターニングポイントになって、さらにいろんな交通問題に関わるきっかけになったという感じです。
そんな経験もあって、その後に本省に戻った時には「交通のことがやりたい」という希望をだしましたが、聞き入れてもらえず、交通以外の部署に配属され、交通に関わる時間を持ちたいと思っていた矢先に、いまの会社(株式会社みちのりホールディングス)に声をかけてもらったので、転職したという流れです。
――ちょっと個人的な事柄に入っちゃうかもしれないですけれど、奥様の影響というのもありますでしょうか?
そうですね。妻は国土交通省の職員なんですけど、もともとはIT企業で働いていました。そんななか、まちづくりをやりたいというので、僕が国交省を勧めて、それで転職したんですね。そこで彼女が楽しく仕事をしているのを見て、自分も行こうかなと思ったのはあります。
それから小山市にいた頃は、大きく影響を受けていました。彼女も一緒に小山市に引っ越ししてきてくれて、国交省都市局のウォーカブルシティの政策担当をしていました。そんなこともあって一緒にフランス旅行に行ったんですが、行ってみるとフランスって、僕らの価値観からするとすごくちゃんとできているんですよね。交通税2っていう財源確保の仕組みをしっかりつくっていて、かつ、まちなかにトランジットモールができていて、そこにLRTを通しているっていう、交通の教科書みたいなまちです。
それを一緒に見て、彼女はウォーカブルシティをやろうと、そして僕は小山市でフランスみたいなまちを実現しようみたいなことを、日々、2人で話し合っていました。
加えて、彼女は子育てしやすいまちをつくるにはどうしたらよいかということと、都市空間のあり方に興味を持っていて、僕は都市の中でも交通機能である「運ぶ」っていう方に興味を持っていて、同じ方向を向いているんですがちょっと分担が違うので、意見交換をよくしているところがあります。
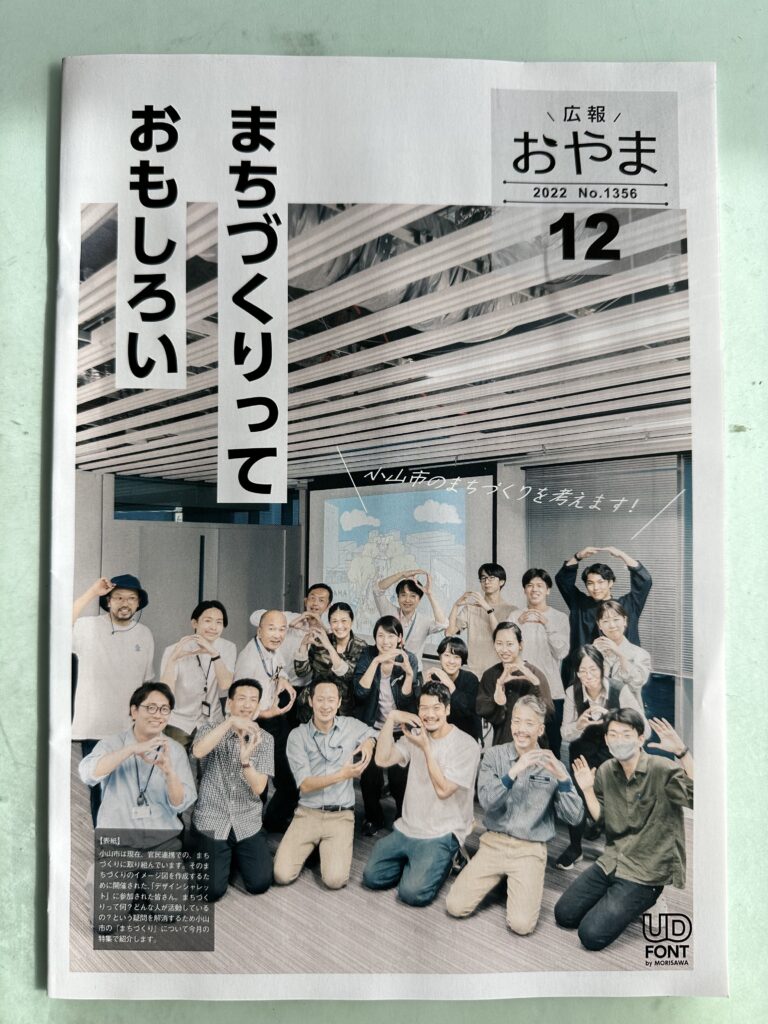

――ありがとうございます。では、淺見さんのキャリアに影響を与えた書籍などについて、お伺いできますでしょうか?
まず1冊目は、『自動車の社会的費用3』です。たしか学部3年生のときに古本屋で偶然見つけて、特に名著だと知らなかったんですけど、読んですごい衝撃を受けたんですね。「自動車ってこんなに社会に迷惑かけてるのか」って。それまで車が大好きだったんですよ。車社会がもう最高のまちだなと思っていたんですけど、大きく価値観を変えられました。
その後、例の土浦のマスタープランのときに、都市問題ってこんなことになっていたのか、どうやって解決するんだろうと思っていたら、『社会的ジレンマの処方箋4』という本に処方箋が書いてあって、なるほどこうすれば確かに解決しそうだなって自分の中ですごく腑に落ちて、それでMMの世界に入っていったんですね。
3冊目は、ごく最近に読んだ『経営リーダーのための社会システム論5』という、都立大の宮台真司先生がもうお一方と話している講義録みたいな本なんですけど、この本から僕が読み取ったのは、結局、自分が影響を与えられる、手の届く範囲でしか、社会課題の解決ってできないんだなということ。それで、大きい政策よりは、自分で改良できる範囲をやりたいなと思ったし、人材育成がすごく大切だという風に思ったんですね。どうしたら良いかって言ったら「寺子屋方式で1人ずつ教え込むしか良い人材は育たない」みたいなことが書いてあったりして(もしかしたら別の場面で宮台先生が言っていた言葉かもしれません)、そのロジックも妙に腑に落ちて。これは自分のいまの価値観の1つをつくるような、良い本でしたね。
――ここまでお伺いしてきた淺見さんのキャリアの中で、苦労話とか悔しい経験などありましたらお願いします。
小山市役所時代には、色々学びました。僕が市役所で何かやろうとして、色んな人に怒られました。議会だったり、市役所だったり、タクシー会社など。。
例えば1つには、市長からの指示で補正予算を計上して、バス路線を引くっていう仕事があったんです。それで、タクシー会社には「タクシーの利用者が減る」って怒られて、議会には「事前にまったく説明もなしになんでそんなことやってるんだ」って怒られて、それから市長には「大々的にやるんだからもっとPRしろ」って怒られて、三者三様に怒られました。「PRしたい」っていう主張と、「いやいや、まだ説明してないんで、プレスリリースなんて全然できないです」みたいな、板挟みの状況に置かれて。あのときは市役所の中の論理がまったくわかっていなかったので、すごく苦労して怒られながら、バスを通しました。
おかげで、市役所で何かするときの勘所っていうものを覚えました。いろんな人に怒られたんで、同じ失敗をしなくなった。議会にはいつ話せば良いのかとか、市長肝入りの案件はどれぐらいの度合いでPRすればいいのかとか、タクシー会社へのケアにしても、いつの時点で何をすればいいのかとか、すごく勉強になったなという感じです。
――そこで学んだ「うまくやる方法」みたいなものを、簡単にご説明いただくことはできますか?
議会だと、時間軸に乗せるってことがすごく大切で。予算をつくるとか、予算の説明をするっていうのは、行政の仕組みで予定されていることなので、そこにしっかり乗せれば、新しいことでもだいたい反対されることが無いことが多い。
あるいは、違うタイミングにイレギュラーで入っていく場合には、ある一定以上の役職の人間が、ステークホルダーのキーマン1人ずつにしっかり説明に行けば、そこでもう大体OKになるので、これはまさに根回しですよね。
これ、正直にいえば正しい姿では全然ないと思うんですけどね。「何をやるか」より、「誰がいつ」の方が大切だったりするので、これでよいのかなとは思います。

Part II 人材育成を語る
――さて、お話は広がりますが、「地域の公共交通課題の解決を担う人材の理想像」について、淺見さんのお考えをお聞かせいただけますでしょうか。
その質問を聞いて思い浮かんだというか、自分が意識していた人が、ニューヨークのサディク=カーン6さんとか、富山市の森雅史(元)7市長だったんですよね。最初に「どういうまちを作りたいか」ということを提示して、さらにそれをしっかりと実現している。そして、それに至るまでのロードマップを、実現可能なかたちでつくっている。その上で、そこには色んな仲間がいるからこそ実現できたし、信じる力もそうでしょうし、発言力というか影響力…人間力みたいなものがあるから、実現できたんだろうなと思います。
――引き合いに出されたサディク=カーンさんのどの部分がとか、森元市長のどこが理想的だとかいうのはありますか?
一番強いなと思うのは、わかりやすいメッセージをつくって、それが伝わっているってところでしょうか。例えば森さんだと、上質な暮らしをするのに、クルマじゃなくてLRTに乗って、コンサートに行ってワインを飲みましょうとか。そういう、なんだろうな…みんなが深く納得するビジョンを提示して、それを実現しているのがすごいなと、思っていたんですよね。
――では、ご説明いただいたような理想像の人材を育成するために、どのような事項が必要だと考えていらっしゃいますでしょうか。
僕はいつも実行する立場にいることが多いので、「決める人間」っていうのが大切だと思っていて。つまり、責任者としての経験が必要だと思うんですよね。それというのはまあ、常にリスクを取るということでもある。失敗もするだろうし、なんなら現状より悪くなる可能性もあるんですけれど、そのリスクをちゃんと取る。
で、失敗すると…じゃあ次はどうしようとか、もしくは失敗を小さくしておいて、軌道修正をしようとか、そういうことができる。ですからプロジェクトが重要ですね。プロジェクトの中で、こういう経験を積むことができるということ。
それから、僕も小山市での仕事を通して思ったんですけど、人に話す経験というのも、すごく大切だなと思いました。それによって自分のやっていることが、何かこう、わかりやすくなるし、それが市民というかユーザーにも伝わるし。こんな風に伝わっているのなら、次はこうしなきゃいけないなみたいなフィードバックが、自分にもあるものです。
そして最後に、やりたいことを最後までやり切ることができる環境。これは僕、公務員だったのでつくづく思うんですけど、人事異動で途中までしかやれないということが結構あるんですよね。それからJRなんて1年で異動だったので、プロジェクトを最後まで見れないみたいな経験が多くて。先にお話しした「責任やリスクを取る」っていうことと、この「ちゃんと最初から最後まで見る、やり切る」というのは、セットになっている話かなと思います。
――責任のお話に関していえば、部下の仕事を見て「あ、これ多分失敗するな」と思っても、淺見さんは黙っているわけですよね。それは相当勇気がいりますね。
そうですね。その代わり、致命的にならないかとか、まあ自分の責任の範囲では、判断してやらせておくっていうか。特に部下がいた市役所のときは、あんまり口を出さないで、考えたことを最後までやってもらって、当事者は失敗もするし、こちらから失敗をちゃんと伝えるっていうことを意識していました。
上司が1から10まで言って、それでできるようになった人間って本当に応用力がないというか、言われないとできなくなっちゃっているし、本当の課題みたいなものを見つける力がない気がしていて。そこはもう「人が死ぬ以外はそんなたいした失敗じゃないかな」とか、それぐらいで放置することを意識しています。
小山市の仕事で1回目のグッドデザイン賞をもらって、皆さんにすごく褒めていただいたときに「いや、淺見がいなくなったらどうするんだ」って方々から言われまして、人材育成についてよく考えるようになりました。ですから2020年ぐらいから意識するようになった感じですね。これは現時点での僕の考えなので、5年後にも同じこと言っているのかどうか、ちょっと自信がないですけど。
――あとは「人に話す」というお話がありましたが、単に上司とか部下とか、同僚と話すだけじゃなくて、例えば講演など、不特定ないろんな人に話すことも含んでいますか?
そうです。研究もそうですし、声をかけて色々話そうというときに、まず自分のやったことをちゃんと一般化して話そうとか、面白くして話そうとか、何か頭の中で巡らせてアウトプットするときの努力というのはすごく大事です。それは、プロジェクトを回すのとは違う思考でやるので。
――それから「最後までやり切ることができる環境」というのは組織の話だと思うんですが、これはやっぱり、公務員とかJRに対して…?
そうですね、これは僕、ずっとそう思っていて。なんか本当に、専門性とか、ある分野のことについてちゃんとできる人間が育たない仕組みだなと思います。
――この1-3年で異動させる仕組みが続く理由は、やはり2年とか3年同じ部署に居ると、付き合いのある業者と癒着して談合、みたいなことがずっとあったからだと聞きます。だから、専門性が育たないリスクがあっても、この仕組みを続けざるをえないと。
それって、別の仕組みでリスクを排除できないのかなって思います。
――加えてその組織が、従業員を従業員として信頼していないということですよね。たしかに、根本的におかしい部分があるのかもしれません。
はい、できたら若いうちから、何か任される経験、やり切る経験とかはした方がいいと思います。
自分のJR時代の失敗にちょっと触れるんですけど、入社2年目の時に、上司がまったく余裕がなくて面倒を見てくれなくて、自分でやらなきゃいけないプロジェクトが三つぐらいいっぺんにあって。あれは相当苦しくてつらかったんですけど、まあ、自分の頭の中が切り変わったって意味では、一つの経験でした。
その時は、めちゃくちゃ失敗してました。すんごい怒られましたし、なんか致命的な失敗に繋がってるような気がしなくもないんですけど。まあ、それは…
――差し支えない範囲で、どういう感じの失敗だったんですか?
そうですね、いっぱいありすぎて。1つは、ある地域の地下自由通路をつくる設計と工事を担当したときの話です。工事費をコストダウンさせてほしいと市役所から言われて。そのために、屋根の設計を変えたんですね。上司がまったく見てくれないんで自分で考えて、設計会社と打ち合わせして進めたんですが、いま思うと「なんであんな屋根つくったんだろう」っていうものができあがって、すごい後悔してます。
こうして言ってても恥ずかしくなるような設計の屋根だったので、「次にはこうしたい」という強い気持ちが生まれる経験だったなというのと。いつでもちゃんと最後の最後まで考え抜かないといけないよなとか、ユーザーからは最後どう見えるのか考えないといけないよなっていう、自分の中での戒めになっていますね、あの屋根は。見た目とか地域のシンボル性で見るとあれで良かったのかなと、未だに思います。
もう1件も行政絡みで、当時たしか全部で15億円くらいの工事の協定を結んでいたのを、そろそろプロジェクトが終わるので使う見込みのない2億円くらいを市役所に返しましょうっていう会議を開くことになりました。上司からはほとんど指示がなく、僕が会議の資料づくり、ロジ(ロジスティクス)とか、全部担ったんですよ。
それで当日は上司が全部ちゃんと仕切ってくれるもんだと思っていたら、そもそも上司が来なくて、僕しかいなくてですね。周りはほとんどが上司くらいの年齢・役職の出席者でした。そんななか、まったく準備不足の状態になっていて。上司がいる前提の僕の甘えもおかしかったんですけど、このときに――社会人の2年目だったかな――全部自分で最初から最後までやるものなんだなと。こういう上司みたいな人間もいるし、自分が最後は全部やらないと場が成り立たないというのを経験したんです。
――その上司は、良い上司だった?
いや、自分的には、もうとんでもなく悪い上司でしたね。反面教師というか、ああいう人間にはなっちゃいけないなっていうのはずっと思ってます。ですから、相手のキャパシティを見て任せないといけないなとは思います。
――人材の育成に関してですけれども、「全部の要素があらかじめ揃っている」という部下はもちろん入ってこないと思いますので、ではどんな素質を持っていれば育てやすいとか、そういったことがあればお聞かせください。
難しいですね。僕自身も答えは持っていないです。 1つ言えるのは、自分の言葉で考えて行動していたり、他者から信頼されていたりということがあると、この人は信頼していいのかなっていう気がします。組織の外からの信頼だと、より良いですよね。例えば市役所だったら、他の部署からよく相談に乗ってるところをみると、この人、市役所の中ですごく信頼を持たれているんだなと思います。
――先ほどの、2年目に付いた上司がまったく見てくれなかったというところにすごく考えさせられるところがありまして。おそらく会社としても「この上司はこういう人間だ」というのはわかっているはずで、その下で失敗をしたところで、バッテンが付かないというような文化があったんでしょうか。多少意思を持ってはみ出す人を、うまく活かせる組織文化というのは、重要なのではないかと。
それは本当にそう思います。4年目ぐらいで、いまお話にあったような本当に放っといてくれる上司に付いて、その方は忙しいからではなくて、ただ見守りおじさんのようにそこにいるっていう状態で放っておいてくれて、任せてくれているという感覚があったので、ずいぶん好きなようにできて、その時は楽しかった。
その後に行った開発調査系っていう、社内の交通データを分析して、地方路線をどうするかを検討する部署なんかでは、本当に好き勝手にやって、割とまわりが納得するアウトプットを出せました。それらを思い返すと、JRの中でも、変な人間を放っておいてくれる文化があったんだなと思います。
――モビリティプロデューサーをどう育成するかという観点からは、すごく重要なお話なのではないかと思って伺っていました。それから淺見さんは、「自分のキャリアプランを作る、実行する」ということを重視しておいでとのことですが。
そうですね。海外の話で、僕も又聞きなので1次情報じゃないんですけど、よく行政の専門職が、公募で誰でも応募できるようになっていて、それで交通部門の責任者とかプロジェクトの責任者になれると聞くんですね。そこでは当然、資格持ちが多い、ドクター持ちが条件になることが多いと聞き、日本もそうなったら良いのになと思うんです。公務員の中で、専門知識が全然ない人が「教えてください」みたいなレベルで異動してきて、1から話すのは大変ですし。実際、小山市でもそういう状況でした。
そういう意味で、海外から聞こえてくる世界観を志向して、自分はどういうポジションで次の仕事をしたいのかということを意識した上で、異動だったり転職だったりをするように心がけているんです。僕みたいにやってほしいとは思わないですけど、やりたいことをやるために、職場を変えることができるというのは重要だと思います。
――ということは、むしろ組織のお話でしょうか。自分でキャリアプランを作るというのは、何かやりたいことをやるために、それをやりやすい組織に変えていくこと?
これはまあ、どっちもじゃないでしょうか。自分自身の話でもあるし、組織の作り方の話でもある。自分がこうありたいという姿に対して職場を選ぶっていうのもありますし、上司としてこういう人材を作りたいというのであれば、ある程度コースに沿った運用――何かその人材の興味関心に沿った仕事を選べるような環境を作っていくことが大切だと思います。自分でも、それが100%できるとは思っていないんですけどね。
――淺見さんのお話を聞いていると、ずっと以前から自分のやりたいことが決まっている印象があって、それがいまもブレていないように感じます。ただ一方で、やりたいことがわからない、キャリアプランなんてデザインできないみたいな人もいると思います。そういう人はどう行動すればよいか、みたいなことに関しては。
これも一般解じゃないんですけど、 色々な職場での経験を積み重ねることと、人と向き合って人事運用をする。
市役所のときにすごく意識してたんことで、1つ目は、市役所だけだと本当に視野が狭くなってしまうので、出向先を開拓して、若い人間(市役所職員)をよく出向させるようにしていました。そうすると、やりたい仕事というのが出てくるでしょうし、見つけられると思うんですね。そこでちゃんとその人間と話をして、何がしたいのかとか、どこに行きたいのかということを言ってもらうようにはしていました。その上で、いまの仕事がもっとしたいならやってほしいし、あるいは本当にそこに引き続き居る必要があるのかとか…これは結構大変でしたけど、一生懸命希望に沿うようにやっていましたね。
――いろいろ体験をさせて、「あ、これ合ってるな」みたいなのを探させる感じで。
そうですね、探してもらうと良いんじゃないかと思います。僕自身の話で言えば、正直、 JRに入社したことを後悔することが多かったんですよ、当時。よく6年も働いたなと思っていて。ただ、それがいまに全然活きていないかといったらそんなことはなくて。
交通事業の土木分野のすべての工程を経験させてもらったので、折々に仕事で役立ちますし、「ゼネコンとしてはどう考えているか」「設計会社の人はどう考えるのか」といった想像も付く。そういう接点がすごく多かったのは、感謝しています。
あれがあったから今があるって言っちゃえば、まあ、それはそうなんですよね。ただ、嫌々でも何か経験したことがあるというのと、こだわってこだわって、好きなことばかりやって、嫌なことは避けて経験しないのとっていうのでは、どっちがいいのか、正直測りかねますね。
――確かに。人生、2回経験できないですから、違う人生を比較しようがないですね。ところで先ほどのお話で、「1年で異動とかはあまり良くないかもしれない」ということと、そうは言っても「色んな仕事を経験した方がいい」っていうところは、どう折り合いをつければ良いのでしょうか。
年数というのは、1つありますよね。JRとか国の総合職の1~2年というのはちょっと短すぎて、4年くらいは居てもいい気はしました。ただ、小山市に5年いてちょっと長いなと思っていたので、、どうなんだろうな…人にもよるし、節目みたいなものがあるんですよね。ただ、1人ずつの節目や希望を聞いていたら、人事異動のパズルがまったく組めないというのもわかるし、答えって、ないんでしょうね。
――いえ、考え続けなければいけないことだとは思います。
次で最後の質問になります。若干戻らせていただきたいのですが、理想に近い人材育成の取組みのところでお話しいただいた内容があったかと思います。 OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)、要は業務の中で、さまざまな経験をするのが大事だろうというお話だったんですが、やはり「業務を通じて」という点が大事だとお考えなんでしょうか。
はい、ありがとうございます。業務を通じて以外にも、研修は必要だと思います。
僕がここのところ、ずっと必要だなと思っている研修があります。まちづくり系で多いかたちのものなんですけど、まず、具体的なフィールドを研修で提示する。それで研修を受ける側は、自分が実践することを前提にして、解決策を考え、提案して、何らかのフィードバックをもらい、最後、案にまで落とし込むんです。それで研修が終わったらそれを実践するという、そういう約束の上での研修なんです。
先にお話しした、「最終決定者」とか「実行する」っていうのは、実務はもちろん、研修においても重要です。いわゆる一般論とか知識を身につける以上のこと、プランをちゃんと作る、責任者として作るまでの経験が必要かなと思います。ですからOJTだけじゃなくてオフの場面でも、こういった視点で研修ツールを作る必要があるのかなと、自分は考えています。
(了)

- 交通弱者:自動車中心社会において,移動を制約される人.高齢者や,子供,身体障碍者,低所得者など. ↩︎
- 交通税:モビリティ負担金制度(Versement mobilite). ↩︎
- 宇沢弘文『自動車の社会的費用』,岩波新書,1974. ↩︎
- 藤井聡『社会的ジレンマの処方箋』,ナカニシヤ出版,2003. ↩︎
- 宮台真司, 野田智義『経営リーダーのための社会システム論』, 光文社, 2022. ↩︎
- ジャネット・サディク=カーン:ブルームバーグ・アソシエイツ代表.2007年から13年までブルームバーグ市長の下でニューヨーク市交通局局長を務め、歩行者や自転車に優しい街路改革を主導. ↩︎
- 森雅史:元富山市長.JR西日本の赤字路線をLRT(次世代型路面電車)「富山ライトレール」として再生させた. ↩︎